2014年01月24日
六郷たんけん隊
こんにちは
復興応援 工藤です
1月23日、六郷市民センターで行われました「子どもたちに伝えたい平成の六郷の暮らし~平成の六郷を振り返る」授業「六郷たんけん隊」に参加してきました
(主催:若林区中央市民センター・六郷市民センター)
子どもたちに自然豊かだった六郷地域の生活の記憶を伝えることを目的としています。
この日は元気いっぱいな六郷小学校の子ども達が集まり、六郷に関連したゲームをしました

続きを読む

復興応援 工藤です

1月23日、六郷市民センターで行われました「子どもたちに伝えたい平成の六郷の暮らし~平成の六郷を振り返る」授業「六郷たんけん隊」に参加してきました

(主催:若林区中央市民センター・六郷市民センター)
子どもたちに自然豊かだった六郷地域の生活の記憶を伝えることを目的としています。
この日は元気いっぱいな六郷小学校の子ども達が集まり、六郷に関連したゲームをしました


続きを読む
2013年12月02日
三本塚オモイデゴハン!
こんにちは
復興応援隊 工藤です

秋もあっという間に終わり寒くて辛い季節がやってきますね
私の周りでは風邪で体調を崩している人が増えているので、体調管理には十分気を付けましょう
さて11月24日の日曜日、三本塚の仮設集会所にて「三本塚オモイデゴハン」が行われるということで参加してきました。
「三本塚オモイデゴハン」は仙台市公益財団法人仙台市市民文化事業団様主催の事業で、三本塚地域で採れた野菜を使い、その地域で昔から食べられてきた料理を三本塚地域の住人が持ち寄り、参加者の皆様と味わうことをメインとしたプロジェクトです。

続きを読む

復興応援隊 工藤です


秋もあっという間に終わり寒くて辛い季節がやってきますね

私の周りでは風邪で体調を崩している人が増えているので、体調管理には十分気を付けましょう

さて11月24日の日曜日、三本塚の仮設集会所にて「三本塚オモイデゴハン」が行われるということで参加してきました。
「三本塚オモイデゴハン」は仙台市公益財団法人仙台市市民文化事業団様主催の事業で、三本塚地域で採れた野菜を使い、その地域で昔から食べられてきた料理を三本塚地域の住人が持ち寄り、参加者の皆様と味わうことをメインとしたプロジェクトです。

続きを読む
2013年11月29日
ハンドトリートメント講座を開催しました。
こんにちは(^O^)/
花坂です

11月28日、六郷・七郷コミネットでは、
若林区で支援活動を行っている団体、個人を対象に、
ハンドトリートメント講座を開催致しました


講師は千葉ひろみさんです
千葉さんは2000年にタッチケアグループ「マザーズハンド」を立ち上げ、
神奈川県を中心にタッチケアやアロマテラピー&ハーブを生活の中で生かす方法や、
横浜栄・防災ボランティアネットワークのメンバーとして乳幼児を持つ保護者向けの防災講座などを行っています。

公益社団法人 日本アロマ環境協会の北郷さん、湯蓋さんの二名にもお手伝い頂きました。
今回は支援者のみなさんの疲れを癒すプログラムを用意して頂きました

さくらチップに香りをつけ、紅茶のパックに入れた香り袋を作成しました。
リボンを結んでクリスマス柄のシールを貼ったら完成
「仮設のイベントにも良いかも!」と、いろんなアイディアが溢れてきます。

ハンドトリートメント開始です
人の手は温かく、体に触れながらコミュニケーションを取るととてもよい気持ちになります

ホホバオイルを塗って、手の滑りを良くすると共に、アロマの香りでリラックス
マッサージをしてもらうと手もスベスベ

ローズマリーとローズゼラニウムの生の葉をかぐと、独特な強い香りがします

最後はみんなでハーブティーを飲みながら交流会
支援者同士、お話が弾んでいました。

ハンドトリートメント講座はとても良い勉強になりました。
今回の経験を今後の活動に活かし、より良い支援活動を行って参ります。
花坂です


11月28日、六郷・七郷コミネットでは、
若林区で支援活動を行っている団体、個人を対象に、
ハンドトリートメント講座を開催致しました



講師は千葉ひろみさんです

千葉さんは2000年にタッチケアグループ「マザーズハンド」を立ち上げ、
神奈川県を中心にタッチケアやアロマテラピー&ハーブを生活の中で生かす方法や、
横浜栄・防災ボランティアネットワークのメンバーとして乳幼児を持つ保護者向けの防災講座などを行っています。

公益社団法人 日本アロマ環境協会の北郷さん、湯蓋さんの二名にもお手伝い頂きました。
今回は支援者のみなさんの疲れを癒すプログラムを用意して頂きました


さくらチップに香りをつけ、紅茶のパックに入れた香り袋を作成しました。
リボンを結んでクリスマス柄のシールを貼ったら完成

「仮設のイベントにも良いかも!」と、いろんなアイディアが溢れてきます。

ハンドトリートメント開始です

人の手は温かく、体に触れながらコミュニケーションを取るととてもよい気持ちになります


ホホバオイルを塗って、手の滑りを良くすると共に、アロマの香りでリラックス

マッサージをしてもらうと手もスベスベ


ローズマリーとローズゼラニウムの生の葉をかぐと、独特な強い香りがします


最後はみんなでハーブティーを飲みながら交流会

支援者同士、お話が弾んでいました。

ハンドトリートメント講座はとても良い勉強になりました。
今回の経験を今後の活動に活かし、より良い支援活動を行って参ります。
タグ :六郷・七郷コミネット
2013年11月26日
七郷市民まつり!30周年!
こんにちは(^O^)/
花坂です
七郷市民センターでは11月23日、24日と2日間に渡って七郷市民まつりが行われました

花坂は23日だけの参加でしたが、復興応援隊も、六郷・七郷コミネットとして、事前のお手伝いと取材に駆けつけました

2日間とも、とても良いお天気に恵まれ、お祭りを楽しむ方々で賑わいました
写真をたくさん載せましたので、「続きを読む」から御覧下さい。 続きを読む
花坂です

七郷市民センターでは11月23日、24日と2日間に渡って七郷市民まつりが行われました


花坂は23日だけの参加でしたが、復興応援隊も、六郷・七郷コミネットとして、事前のお手伝いと取材に駆けつけました


2日間とも、とても良いお天気に恵まれ、お祭りを楽しむ方々で賑わいました

写真をたくさん載せましたので、「続きを読む」から御覧下さい。 続きを読む
2013年11月15日
"昭和の仙台"8ミリで楽しむっ茶会最終回!
こんにちは(^O^)/
花坂です
最終回となる第19回"昭和の仙台"8ミリで楽しむっ茶会が
11月13日にJR南小泉仮設住宅集会所において行われました。
(主催:六郷・七郷コミネット 企画:20世紀アーカイブ仙台)

仙台は先日初雪を観測し、この日もいよいよ冬というような寒さでした

そのような日にわざわざお集まりいただいた皆様には誠に感謝を申しあげます。

今回も、荒浜にお住まいだった方を対象に
昭和の懐かしの道具、映像、写真の観賞を行い、参加者のみなさんから聞き取りを行いました

こちらはお盆の帰省の様子を撮影した映像です。
お盆には蓮の葉を皿にして柳の木の枝で箸を作り、盆棚に供えていました。
「15日のお盆に盆棚を作ってお仏さんに上げるの。」
「16日には先祖が帰ってしまうから、15日はごちそうであるお餅をついてお迎えをした。」
当時、お餅は最高のごちそうだったけれど、今の若い世代には分からない感覚です

こちらは貞山堀でのシジミ捕りの写真。
シジミをみんなで捕り過ぎた為に、シジミが少なくなって、
近年、稚貝の放流を行うようになっていたようです。
参加者の男性が「橋から100メートル以内はお金を取られるようになったけど、それ以外の場所はタダで捕れた。貝だって動くからね!」
と、100メートル先まで泳いで来た稚貝を捕獲していた事を告白(笑)
…なるほど、貝は動き回るから仕方ないですよね~(゜v゜;)
貞山堀はお米や野菜を洗えるほど水が綺麗だったそうです。
昼は男性がふんどしも着けずに裸で泳ぎ、夜は女性が隠れて泳いでいたというお話で盛り上がりました。
…なるほど、みんなが泳いでる綺麗な水(?)でお米を研いで食べていたわけですね(゜-゜)
今回の楽しむっ茶会は冗談も飛び交う楽しいお話や、びっくりするような習慣など、たくさんお話を聞かせていただきました

全19回行われたこの楽しむっ茶会は現在、聞き取りを行った内容をまとめ、地域誌を作成中です

発行は平成26年3月を予定しています。
花坂です

最終回となる第19回"昭和の仙台"8ミリで楽しむっ茶会が
11月13日にJR南小泉仮設住宅集会所において行われました。
(主催:六郷・七郷コミネット 企画:20世紀アーカイブ仙台)

仙台は先日初雪を観測し、この日もいよいよ冬というような寒さでした


そのような日にわざわざお集まりいただいた皆様には誠に感謝を申しあげます。

今回も、荒浜にお住まいだった方を対象に
昭和の懐かしの道具、映像、写真の観賞を行い、参加者のみなさんから聞き取りを行いました


こちらはお盆の帰省の様子を撮影した映像です。
お盆には蓮の葉を皿にして柳の木の枝で箸を作り、盆棚に供えていました。
「15日のお盆に盆棚を作ってお仏さんに上げるの。」
「16日には先祖が帰ってしまうから、15日はごちそうであるお餅をついてお迎えをした。」
当時、お餅は最高のごちそうだったけれど、今の若い世代には分からない感覚です


こちらは貞山堀でのシジミ捕りの写真。
シジミをみんなで捕り過ぎた為に、シジミが少なくなって、
近年、稚貝の放流を行うようになっていたようです。
参加者の男性が「橋から100メートル以内はお金を取られるようになったけど、それ以外の場所はタダで捕れた。貝だって動くからね!」
と、100メートル先まで泳いで来た稚貝を捕獲していた事を告白(笑)
…なるほど、貝は動き回るから仕方ないですよね~(゜v゜;)
貞山堀はお米や野菜を洗えるほど水が綺麗だったそうです。
昼は男性がふんどしも着けずに裸で泳ぎ、夜は女性が隠れて泳いでいたというお話で盛り上がりました。
…なるほど、みんなが泳いでる綺麗な水(?)でお米を研いで食べていたわけですね(゜-゜)

今回の楽しむっ茶会は冗談も飛び交う楽しいお話や、びっくりするような習慣など、たくさんお話を聞かせていただきました


全19回行われたこの楽しむっ茶会は現在、聞き取りを行った内容をまとめ、地域誌を作成中です


発行は平成26年3月を予定しています。
2013年11月06日
第3回 仙台市震災復興メモリアル等検討委員会
こんばんは
よしだけいしゅん@仙台市若林区復興応援隊です
昨日はせんだいメディアテークで開催された
「第3回 仙台市震災復興メモリアル等検討委員会」を
傍聴してきました
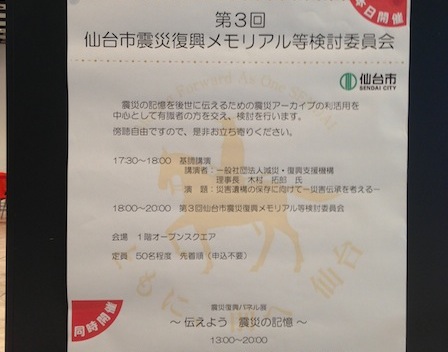

議題は2つ
「震災アーカイブの利活用について」
「震災以降の保存、モニュメント整備の検討状況について」
それぞれの議題について、事務局より進捗等の報告があり
それを受けて、有識者で組織される委員の方々が
色々な提案等をしていくというもの
…
印象的だった話としては
「モノ」を残すことも大切だが
そこにあった「思い」を伝えること
また、どのように伝えるかということも大切
長いスパンで考えること
持続可能なアーカイブの方法が必要
50年、100年後の市民の感覚をイメージする
時期と相手によってアーカイブの使い方をデザインする必要
被災の記録を残すだけではなく
「フィクション」(震災にインスパイアされて作られた作品)を
アーカイブしていく視点
イチかゼロか、ではない
保存が難しくなった段階で、その一部を象徴的なものとして
モニュメント的に再利用することも考えられる
…
続きを読む
よしだけいしゅん@仙台市若林区復興応援隊です
昨日はせんだいメディアテークで開催された
「第3回 仙台市震災復興メモリアル等検討委員会」を
傍聴してきました
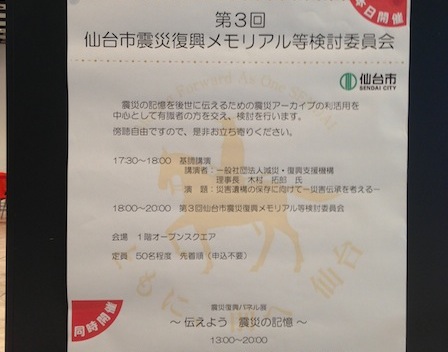

議題は2つ
「震災アーカイブの利活用について」
「震災以降の保存、モニュメント整備の検討状況について」
それぞれの議題について、事務局より進捗等の報告があり
それを受けて、有識者で組織される委員の方々が
色々な提案等をしていくというもの
…
印象的だった話としては
「モノ」を残すことも大切だが
そこにあった「思い」を伝えること
また、どのように伝えるかということも大切
長いスパンで考えること
持続可能なアーカイブの方法が必要
50年、100年後の市民の感覚をイメージする
時期と相手によってアーカイブの使い方をデザインする必要
被災の記録を残すだけではなく
「フィクション」(震災にインスパイアされて作られた作品)を
アーカイブしていく視点
イチかゼロか、ではない
保存が難しくなった段階で、その一部を象徴的なものとして
モニュメント的に再利用することも考えられる
…
続きを読む
2013年10月04日
"昭和の仙台"8ミリで楽しむっ茶会18回目!
10月3日は18回目の"昭和の仙台"8ミリで楽しむっ茶会が七郷中央公園仮設住宅で行われました。
(六郷・七郷コミネット企画/20世紀アーカイブ仙台主催)

七郷中央公園仮設で行うのは今回が初めてです
20世紀アーカイブ仙台さんのプログラム構成も素晴らしく
懐かしの道具、映像、画像、音楽と盛りだくさんの内容をご鑑賞頂きました

こちら手にもっているのは昔、富山の薬売りさんが配っていた紙風船です。
「富山の薬売りさんが、あの頃は家庭を自転車やバイクで回っていた」
「いろんな話をしてくれて面白おかしく薬を売っていたんだよ」
とお話が盛り上がりました

こちらの木の棒のようなものは「ふけだい」という布を張る時に使う裁縫道具の一つです。
「今でも便利!ふける時に使う」
「売ってるなら今でも欲しいね」
という声が上がり、他の参加者の方から「それを貰ったらいいさ!」と、見本を指差して冗談を言う場面もありました。
会場から笑いが起こりとても賑やかでした

仙台の民謡、「おいとこ節」の映像を見ながら懐かしさに口ずさむ方もいらっしゃいました
「おいとこ節は父親のおはこだった。お酒を飲まない人だったけど、何かあると必ず歌ったの。テープに録っていたけど、津波で流されてしまったね」

この日のメインとなったのは、「仙台浜の漁業」という平成8年頃の荒浜漁の映像です
荒浜、深沼出身の方のお知り合いや親せきが多く出演していて、「○○おんつぁんださー!あらー!」「○○ちゃんじゃないの!?」「この人は井土浜の人だよ」と歓声が上がり、
亡くなった方の生前の姿を見て涙する方もいらっしゃいました

恒例の貞山堀で行われていたシジミ捕りの写真が登場
ここでシジミ採りの新事実が発覚。
昭和の中ごろまでは誰でも自由にシジミ捕りが出来ていましたが、後期には漁業権がないと一般の人は捕る事ができなくなってしまったそうです。
今は勝手に採ってはいけないんですね

今回もいろんな思い出話をたくさん聞く事が出来ました
地域誌を作る為に聞き取りを行っている楽しむっ茶会ですが、「これから活かす」事も大事、でも「今」を生きる人に喜んでいただけることも大切な事だと感じる回でした
(六郷・七郷コミネット企画/20世紀アーカイブ仙台主催)

七郷中央公園仮設で行うのは今回が初めてです

20世紀アーカイブ仙台さんのプログラム構成も素晴らしく

懐かしの道具、映像、画像、音楽と盛りだくさんの内容をご鑑賞頂きました


こちら手にもっているのは昔、富山の薬売りさんが配っていた紙風船です。
「富山の薬売りさんが、あの頃は家庭を自転車やバイクで回っていた」
「いろんな話をしてくれて面白おかしく薬を売っていたんだよ」
とお話が盛り上がりました


こちらの木の棒のようなものは「ふけだい」という布を張る時に使う裁縫道具の一つです。
「今でも便利!ふける時に使う」
「売ってるなら今でも欲しいね」
という声が上がり、他の参加者の方から「それを貰ったらいいさ!」と、見本を指差して冗談を言う場面もありました。
会場から笑いが起こりとても賑やかでした


仙台の民謡、「おいとこ節」の映像を見ながら懐かしさに口ずさむ方もいらっしゃいました

「おいとこ節は父親のおはこだった。お酒を飲まない人だったけど、何かあると必ず歌ったの。テープに録っていたけど、津波で流されてしまったね」

この日のメインとなったのは、「仙台浜の漁業」という平成8年頃の荒浜漁の映像です

荒浜、深沼出身の方のお知り合いや親せきが多く出演していて、「○○おんつぁんださー!あらー!」「○○ちゃんじゃないの!?」「この人は井土浜の人だよ」と歓声が上がり、
亡くなった方の生前の姿を見て涙する方もいらっしゃいました


恒例の貞山堀で行われていたシジミ捕りの写真が登場

ここでシジミ採りの新事実が発覚。
昭和の中ごろまでは誰でも自由にシジミ捕りが出来ていましたが、後期には漁業権がないと一般の人は捕る事ができなくなってしまったそうです。
今は勝手に採ってはいけないんですね


今回もいろんな思い出話をたくさん聞く事が出来ました

地域誌を作る為に聞き取りを行っている楽しむっ茶会ですが、「これから活かす」事も大事、でも「今」を生きる人に喜んでいただけることも大切な事だと感じる回でした

2013年09月27日
"昭和の仙台"8ミリで楽しむっ茶会17回目!
こんにちは(^O^)/
花坂です
9月25日には
17回目を迎える”昭和の仙台”8ミリで楽しむっ茶会がニッペリア仮設住宅で行われました
(六郷・七郷コミネット企画/20世紀アーカイブ仙台主催)

前回とは内容が変わって、こちらは初登場 緑色の蚊帳です
緑色の蚊帳です
何故かはわかりませんが、緑と水色の蚊帳が主流だったそうです
私にとって、となりのト○ロでしか見たことが無かった蚊帳が目の前に…感動の対面です
しかしみなさん当たり前のように、「ああ、蚊帳だね」という感想。
幼いころから見なれた存在なのですね

「ラブリーせんだい」という番組の映像を観賞しました
映像に写っている井戸浜で藍染を行った記録、『葉藍仕入れ台帳』の持ち主の男性、
参加者の中に同級生が居たようです
楽しむっ茶会でお見せする映像の中に、毎回必ずと言っていいほど
参加者のお知り合いが写っているのが凄いですね
みなさんネットワークが広い


こちらは昭和二年生まれの黒川さんという方が描きとめた『昭和見聞録』を観賞しているところです
仙台の昭和時代の様子が描かれています

みなさん、
「ああ、紙芝居屋も居たね」
「ドンドン焼きも食べたね」
「ネギとそぼろなんかを入れておやつとして食べたの」
と懐かしそうに語っていました。

前回、サンピアで行った楽しむっ茶会で話題に出た「ぬ゛」については
やはりみなさん御存じで、
「油揚げを煮て、セリなどを乗せるんだよね」
「煮付けとも違うし、お吸い物でもない、お葬式の時に出すね」
必ず正四角形に切った特別な油揚げを使って作ったそうです
他にも、ご飯に四角の落雁が入っている「カク」という精進料理もあったそうです。
また、精進料理全体を「カク」と呼ぶとか
お葬式の時には四角い食べ物を食べるとは不思議です。
「四角」には何か意味がありそうですね


花坂です

9月25日には
17回目を迎える”昭和の仙台”8ミリで楽しむっ茶会がニッペリア仮設住宅で行われました

(六郷・七郷コミネット企画/20世紀アーカイブ仙台主催)

前回とは内容が変わって、こちらは初登場
 緑色の蚊帳です
緑色の蚊帳です
何故かはわかりませんが、緑と水色の蚊帳が主流だったそうです

私にとって、となりのト○ロでしか見たことが無かった蚊帳が目の前に…感動の対面です

しかしみなさん当たり前のように、「ああ、蚊帳だね」という感想。
幼いころから見なれた存在なのですね


「ラブリーせんだい」という番組の映像を観賞しました

映像に写っている井戸浜で藍染を行った記録、『葉藍仕入れ台帳』の持ち主の男性、
参加者の中に同級生が居たようです

楽しむっ茶会でお見せする映像の中に、毎回必ずと言っていいほど
参加者のお知り合いが写っているのが凄いですね

みなさんネットワークが広い



こちらは昭和二年生まれの黒川さんという方が描きとめた『昭和見聞録』を観賞しているところです

仙台の昭和時代の様子が描かれています


みなさん、
「ああ、紙芝居屋も居たね」
「ドンドン焼きも食べたね」
「ネギとそぼろなんかを入れておやつとして食べたの」
と懐かしそうに語っていました。

前回、サンピアで行った楽しむっ茶会で話題に出た「ぬ゛」については
やはりみなさん御存じで、
「油揚げを煮て、セリなどを乗せるんだよね」
「煮付けとも違うし、お吸い物でもない、お葬式の時に出すね」
必ず正四角形に切った特別な油揚げを使って作ったそうです

他にも、ご飯に四角の落雁が入っている「カク」という精進料理もあったそうです。
また、精進料理全体を「カク」と呼ぶとか

お葬式の時には四角い食べ物を食べるとは不思議です。
「四角」には何か意味がありそうですね



2013年09月11日
"昭和の仙台"8ミリで楽しむっ茶会16回目!
9月4日は16回目の"昭和の仙台"8ミリで楽しむっ茶会を行いました。
(六郷・七郷コミネット企画、20世紀アーカイブ仙台主催)

今回はサンピアで七郷地区のみなし仮設にお住まいの方を対象に、11名にお集まりいただきました
この日は「ジッとしていられないの」と言って立ち上がり、
茄子とキュウリのお漬物を準備して御馳走して下さるなど、アクティブな方が多く参加されました。

「深沼は野菜がいっぱい採れたからどこの家でも漬物を漬けたんだよ」

さすが伝統の腕前
売っている漬物では味わえないとても美味しいお漬物でした。
さて今回の楽しむっ茶会ですが

こちらの葛篭の中から懐かしい道具達が顔を出します
かすりの反物やのっこ、サイカチの実など、どれも参加者の記憶に残る懐かしい思い出の品です。

こちらの煙管は「どらんこ」という小さなキーケースのような皮袋に入っているものです。
「行儀が悪かったりすると、しつけの為に、これで叩かれたのよ」と、語る方も。
この道具は参加者の皆様よりもずっと年上の世代、おじいさんやおっぴさん(曾祖母、曾祖父)が使っていた道具だそうです。
震災より少し前の荒浜地区、貞山堀にかかる貞山橋の北側から閖上方面を撮った写真を観賞中に
「一番左側の手前に、家が写ってる!」
なんと、参加者の中に、写真に写っているお家の家主がいらっしゃいました

同じく貞山堀でのシジミ採りの写真からお話は広がり、
「海では波の子貝を採って食べたんだよ」
「波の子は醤油、砂糖で佃煮にして食べるんです」
「採れたのは蒲生だけでないよ、深沼でも沢山採れたんだから!」
と、波の子が採れるスッポト自慢が始まりました
波の子貝は水につけっぱなしにしておくと、足が早いので、貝にあたりやすいそう
いつもあたる人が居て、よく救急車が来ていたんだとか。
それだけ、地元の方々にとってなじみのある貝だったのですね。

地元のみなさんにとってなじみのある食べ物の中に
「に」と「ぬ」の間の発音の食べ物「ぬ゛」というものがあるそうです。
「ぬ゛」を漢字に直すと「煮(に)」と読みます。
お豆腐屋の海野さんが作る、分厚いふわふわの油揚げをみりんと醤油で煮て、生姜を乗せた精進料理。
今は津波でお豆腐屋さんの機械が流され、もう食べられないのだそうです
波の子貝、油揚げ
「また食べたいな…」
参加者のみなさんは、そう呟いていました。

(六郷・七郷コミネット企画、20世紀アーカイブ仙台主催)

今回はサンピアで七郷地区のみなし仮設にお住まいの方を対象に、11名にお集まりいただきました

この日は「ジッとしていられないの」と言って立ち上がり、
茄子とキュウリのお漬物を準備して御馳走して下さるなど、アクティブな方が多く参加されました。

「深沼は野菜がいっぱい採れたからどこの家でも漬物を漬けたんだよ」

さすが伝統の腕前

売っている漬物では味わえないとても美味しいお漬物でした。
さて今回の楽しむっ茶会ですが

こちらの葛篭の中から懐かしい道具達が顔を出します

かすりの反物やのっこ、サイカチの実など、どれも参加者の記憶に残る懐かしい思い出の品です。

こちらの煙管は「どらんこ」という小さなキーケースのような皮袋に入っているものです。
「行儀が悪かったりすると、しつけの為に、これで叩かれたのよ」と、語る方も。
この道具は参加者の皆様よりもずっと年上の世代、おじいさんやおっぴさん(曾祖母、曾祖父)が使っていた道具だそうです。
震災より少し前の荒浜地区、貞山堀にかかる貞山橋の北側から閖上方面を撮った写真を観賞中に
「一番左側の手前に、家が写ってる!」
なんと、参加者の中に、写真に写っているお家の家主がいらっしゃいました


同じく貞山堀でのシジミ採りの写真からお話は広がり、
「海では波の子貝を採って食べたんだよ」
「波の子は醤油、砂糖で佃煮にして食べるんです」
「採れたのは蒲生だけでないよ、深沼でも沢山採れたんだから!」
と、波の子が採れるスッポト自慢が始まりました

波の子貝は水につけっぱなしにしておくと、足が早いので、貝にあたりやすいそう

いつもあたる人が居て、よく救急車が来ていたんだとか。
それだけ、地元の方々にとってなじみのある貝だったのですね。

地元のみなさんにとってなじみのある食べ物の中に
「に」と「ぬ」の間の発音の食べ物「ぬ゛」というものがあるそうです。
「ぬ゛」を漢字に直すと「煮(に)」と読みます。
お豆腐屋の海野さんが作る、分厚いふわふわの油揚げをみりんと醤油で煮て、生姜を乗せた精進料理。
今は津波でお豆腐屋さんの機械が流され、もう食べられないのだそうです

波の子貝、油揚げ
「また食べたいな…」
参加者のみなさんは、そう呟いていました。

2013年09月06日
第3回 若林区復興情報セミナー開催!
8月29日は六郷・七郷コミネット主催で、
「第3回 若林区復興情報セミナー」を開催致しました

復興情報セミナーは、
若林区内の被災者支援活動団体等に対し
仙台市震災復興計画及びその進歩状況を理解して頂くとともに
支援の状況と課題を共有し、今後の各団体の活動の参考にしてもらう事、
また、地域の自立・復興に向け力を発揮していただく事を目的とするものです。

初めに
六郷・七郷コミネット会長 菊池守氏と、
若林区区長 氏家道也氏から主催のご挨拶をいただきました。
前半は「仙台市若林区震災復興の『今』~仙台市復興支援事業と生活再建支援~」
というテーマで若林区副区長 吉岡成二氏より講話がありました。
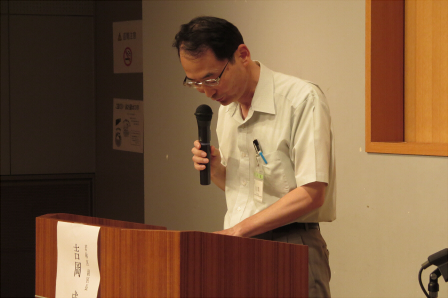
次のステップへとして、復興公営住宅へ移るに時期になり今後、道が別れてゆく被災者への支援をどのようにしていくかが大きな課題であると語る副区長。
副区長からお話を頂いた後は「これからの被災者支援活動」をテーマにパネルディスカッションを行いました。

モデレーターは
[東北学院大学 経済学部 共生社会経済学科 准教授 齊藤康則氏]

パネリストは
[仙台市若林区社会福祉協議会 事務局長 堀英敏氏]
[みやぎ生協 仙塩ボランティアセンター センター長 高橋朋子氏]
[一般財団法人 仙台YWCA 代表理事 伊藤香美子氏]
の三名にお願い致しました。

震災から2年が過ぎ、状況が変化していくにつれて今までの役割分担が不透明化していく中で
若林区では六郷・七郷コミネットや社会福祉協議会で行っている復興の輪ミーティングなど、民間共同で情報交換を行っています。
様々な団体と協力しながらホスト仮設期に向けて今後どうのように支援していくかが課題となっています。
これまでの公的機関、民間企業、市民団体による支援を振り返る為に、
現在まで行って来た活動展開についてそれぞれお話をしていただきました。

後半からは参加者を5グループに分けて車座会議と題しまして、
情報交換会を行いました。
パネルディスカッションでお話を受けた三団体の目線の違いを参考に自由に議論して頂きました。

テーマは「被災された方への生活支援」という事で
仮設から復興公営住宅へ移行していく現在、抱えている課題をそれぞれの立場から情報を共有し、議論した内容をグループ事に発表します。

 仮設から復興公営住宅への移行に向けて被災者が自立していく段階で様々な支援団体の活動をこれまで通り行っていくだけで良いのか。
仮設から復興公営住宅への移行に向けて被災者が自立していく段階で様々な支援団体の活動をこれまで通り行っていくだけで良いのか。
 今後仮設に残されていく自立再建が難しい方々に対して、個別支援、情報共有をどのようにすべきか。
今後仮設に残されていく自立再建が難しい方々に対して、個別支援、情報共有をどのようにすべきか。
 復興公営住宅でのコミュ二ティー形成、リーダーの育成の課題。
復興公営住宅でのコミュ二ティー形成、リーダーの育成の課題。
等の課題がある中で、短い時間では議論がつきず、なかなか纏まらなかったグループもありました。
せっかく様々な立場の皆様にお集まり頂ける貴重な場ですので、
次回はさらに準備を重ねてたくさん議論して頂ける場づくりに努力して参ります。
冬頃開催予定の第4回若林区復興情報セミナーへのご参加もお待ちしております

「第3回 若林区復興情報セミナー」を開催致しました


復興情報セミナーは、
若林区内の被災者支援活動団体等に対し
仙台市震災復興計画及びその進歩状況を理解して頂くとともに
支援の状況と課題を共有し、今後の各団体の活動の参考にしてもらう事、
また、地域の自立・復興に向け力を発揮していただく事を目的とするものです。

初めに
六郷・七郷コミネット会長 菊池守氏と、
若林区区長 氏家道也氏から主催のご挨拶をいただきました。
前半は「仙台市若林区震災復興の『今』~仙台市復興支援事業と生活再建支援~」
というテーマで若林区副区長 吉岡成二氏より講話がありました。
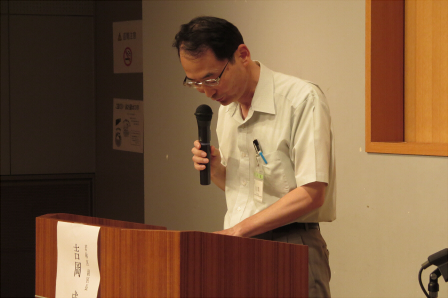
次のステップへとして、復興公営住宅へ移るに時期になり今後、道が別れてゆく被災者への支援をどのようにしていくかが大きな課題であると語る副区長。
副区長からお話を頂いた後は「これからの被災者支援活動」をテーマにパネルディスカッションを行いました。

モデレーターは
[東北学院大学 経済学部 共生社会経済学科 准教授 齊藤康則氏]

パネリストは
[仙台市若林区社会福祉協議会 事務局長 堀英敏氏]
[みやぎ生協 仙塩ボランティアセンター センター長 高橋朋子氏]
[一般財団法人 仙台YWCA 代表理事 伊藤香美子氏]
の三名にお願い致しました。

震災から2年が過ぎ、状況が変化していくにつれて今までの役割分担が不透明化していく中で
若林区では六郷・七郷コミネットや社会福祉協議会で行っている復興の輪ミーティングなど、民間共同で情報交換を行っています。
様々な団体と協力しながらホスト仮設期に向けて今後どうのように支援していくかが課題となっています。
これまでの公的機関、民間企業、市民団体による支援を振り返る為に、
現在まで行って来た活動展開についてそれぞれお話をしていただきました。

後半からは参加者を5グループに分けて車座会議と題しまして、
情報交換会を行いました。
パネルディスカッションでお話を受けた三団体の目線の違いを参考に自由に議論して頂きました。

テーマは「被災された方への生活支援」という事で
仮設から復興公営住宅へ移行していく現在、抱えている課題をそれぞれの立場から情報を共有し、議論した内容をグループ事に発表します。

 仮設から復興公営住宅への移行に向けて被災者が自立していく段階で様々な支援団体の活動をこれまで通り行っていくだけで良いのか。
仮設から復興公営住宅への移行に向けて被災者が自立していく段階で様々な支援団体の活動をこれまで通り行っていくだけで良いのか。 今後仮設に残されていく自立再建が難しい方々に対して、個別支援、情報共有をどのようにすべきか。
今後仮設に残されていく自立再建が難しい方々に対して、個別支援、情報共有をどのようにすべきか。 復興公営住宅でのコミュ二ティー形成、リーダーの育成の課題。
復興公営住宅でのコミュ二ティー形成、リーダーの育成の課題。等の課題がある中で、短い時間では議論がつきず、なかなか纏まらなかったグループもありました。
せっかく様々な立場の皆様にお集まり頂ける貴重な場ですので、
次回はさらに準備を重ねてたくさん議論して頂ける場づくりに努力して参ります。
冬頃開催予定の第4回若林区復興情報セミナーへのご参加もお待ちしております






